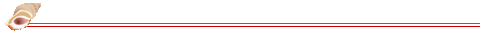ヒラセイゴ(スズキ)の昆布〆&刺身
シーバスと呼ばれるスズキ。東京湾などではゲームフィッシングのターゲットだが、外洋で獲れるスズキは非常に美味。
特に、成魚になると磯に棲むヒラスズキは臭みもなく、その淡泊な白身は料亭で扱われる高級魚である。
その幼魚であるヒラセイゴも、30cmを超えてくると脂が乗り、刺身も上品な甘味が感じられる。
 昆布〆
昆布〆

うろこを落とす。
※どの魚もそうだが、20~30cmを超える魚は釣り上げ後、血抜きすることをお奨めする。鮮度保持もあるが、臭みが各段に異なる。
三枚におろし、腹骨と血合い骨を取り除く。
皮を引く。
水分、臭みを抜くために身に軽く塩を振る。場合により省略してもよい。
昆布を日本酒で拭く。
※昆布の白い粉は旨みのため、決して洗い流してはダメ。日本酒を含ませたキッチンペーパーなどで昆布の表面を湿らす。昆布は利尻、羅臼、日高などお好みで。日高昆布は雑味が出るなどの意見もあるが、特に気にならない。むしろ、昆布の種類による味の濃厚さで〆時間を調節することの方が大切かもしれない。
塩で出た身の水分を拭き取り、昆布でミルフィールのように挟んでいく。
昆布がしっかり密着するようにラップで巻き、冷蔵庫で好みの時間、保管する。
 ※〆る時間は諸説いろいろ。柵の場合は6時間や一晩とか、刺身の切り身は3時間とか。Dr.Kが30㎝程度のセイゴの片身を6時間〆た時は、〆過ぎでグミのよう。これは失敗。(右写真)
※〆る時間は諸説いろいろ。柵の場合は6時間や一晩とか、刺身の切り身は3時間とか。Dr.Kが30㎝程度のセイゴの片身を6時間〆た時は、〆過ぎでグミのよう。これは失敗。(右写真)ある板前さんが「柵でも1時間程度で問題ない。30分でもよい。好みによるが、昆布の風味に刺身の食感、甘みが残っている方が美味い」と言っていたので、同じサイズの片身を1時間で〆たところ、超絶うまし。
魚の脂のりの状態、昆布の種類などによって30分から1時間程度だ。
〆が完了したら、昆布を取り除く。すぐに食べない場合も昆布を取り除いておく。
そぎ切りして盛りつける。
死後硬直によりイノシン酸が増した身に昆布のグルタミン酸。刺身の甘みに昆布の上品なコクが加わった感じ。誰が考えたんだろう?素晴らしい。一度お試しあれ。



 刺身の場合)
刺身の場合)

うろこを落とす。
三枚におろし、腹骨と血合い骨を取り除く。
皮を引く。
そぎ切りして盛りつける。
刺身は昆布〆より爽やかな味わいにほのかな甘み。これはこれで別の食べ物。美味い!